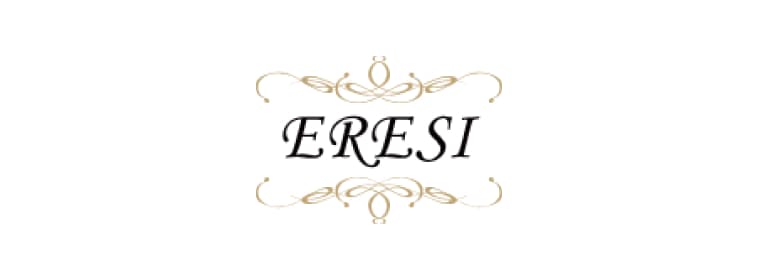目次
「鉄筋コンクリートで、堅牢な住宅を建てたい」
こんな想いで、鉄筋コンクリート住宅の耐震性を調べている方もいるのではないでしょうか。他の構造と比べると、鉄筋コンクリート構造の住宅は耐震性が高い建物です。
本記事では、鉄筋コンクリート住宅の耐震性が高い理由や、他の構造の建物との違いを解説しています。地震に強い住宅を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
鉄筋コンクリート住宅は耐震性が高い

鉄筋コンクリート構造の住宅は、耐震性が高いといわれています。鉄筋とコンクリート、2つの素材の特性を組み合わせることで、耐震性を高めているからです。
鉄筋コンクリート構造とは、コンクリートに鉄筋を入れて一体化した構造を指します。
以下の画像は、住宅の壁や床、天井などを鉄筋コンクリートで成形した状態です。

以下は、コンクリートと鉄筋の揺れに対する特性の比較です。
| 素材 | 圧縮(縦方向に作用する力) | 引張り(横方向に作用する力) |
|---|---|---|
| コンクリート | 強い | 弱い |
| 鉄筋 | 弱い | 強い |
圧縮とは縦方向に作用する力のことで、地震に置き換えると縦揺れを指します。また、引張りは横方向に作用する力を指し、地震における横揺れのことです。
地震の揺れに対して正反対の性質をもつコンクリートと鉄筋を組み合わせていることから、鉄筋コンクリート構造は耐震性が高いといえます。コンクリートを使用する分、重量があり地震発生時の揺れは大きいものの、強度があるため倒壊のリスクは抑えられます。
参考:日本建築学会「1.鉄筋コンクリート構造の特徴」
鉄筋コンクリート構造と比較した他の構造の耐震性
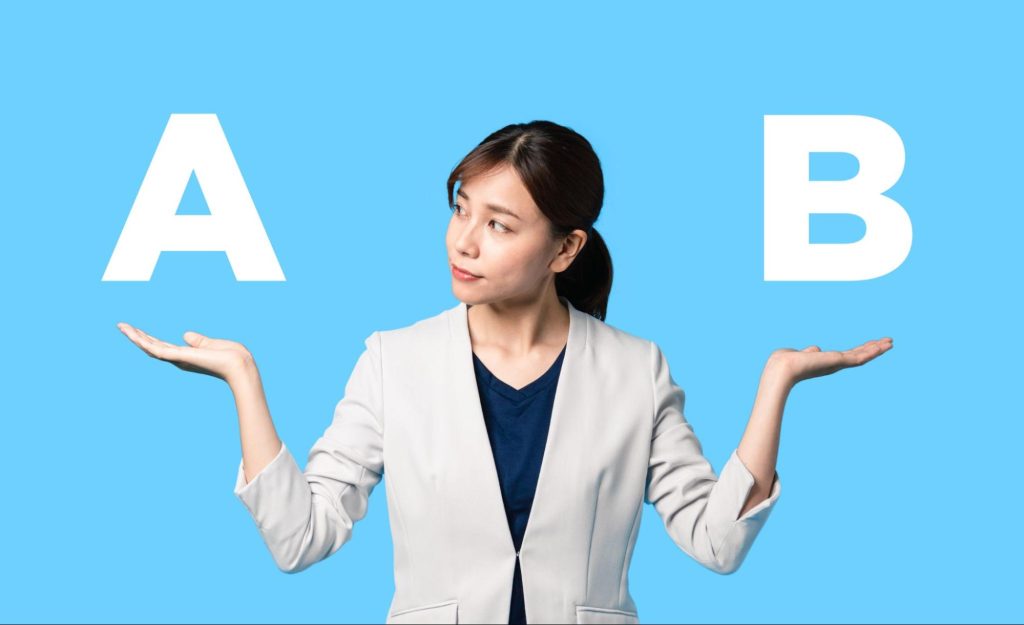
鉄筋コンクリート構造と以下の構造とで、耐震性の違いを比較してみましょう。
- 重量鉄骨造の場合
- 軽量鉄骨造の場合
- 木造の場合
重量鉄骨造の場合
一般的に重量鉄骨造の建物は、耐震性が高いといわれています。しかし、鉄筋コンクリートと比較すると、重量鉄骨造の耐震性は低くなります。
重量鉄骨造とは、建物の骨組みに厚さ6mm以上の鋼や鉄を使用した構造のことです。一般的に、厚さ9〜14mmの骨組みで施工されるケースが多くなっています。
以下の画像は、鉄骨造の建物の骨組みのイメージです。

重量鉄骨造の建物は、骨組みの柱と梁をボルトでつなぎ合わせて固定して、耐震性を高めています。しかし、鋼と鉄はどちらの素材も熱に弱いため、地震の影響で火災が発生した場合は倒壊の懸念があります。
軽量鉄骨造の場合
軽量鉄骨造の住宅は一般的に耐震性が高いといわれていますが、鉄筋コンクリート構造と比較すると、耐震性が低くなります。
軽量鉄骨造は、建物の骨組みに厚さ6mm未満の鋼や鉄を使用した構造です。一般的に、軽量鉄骨造の骨組みは厚さ3〜4mmで施工されるケースが多い傾向にあります。
鋼材や鉄材は揺れが発生した際にしなる特性があるため、大地震でなければ十分に耐えられます。しかし、骨組みの柱や梁に厚さがないため、重量鉄骨造よりも耐震性は低いです。
木造の場合
木造住宅の耐震性は、構造の観点からいうと鉄筋コンクリート住宅に劣ります。しかし実際は、耐震基準を満たすように設計するため、過度な心配は必要ありません。
以下の画像は、木造住宅の構造のイメージです。

木造住宅では、柱と柱の間に斜めに筋交いを入れたり、揺れで柱や梁の構造が変形しないようボードで補強した耐力壁を設置したりすることで、耐震性を持たせています。「木造は地震に弱い」とイメージされがちですが、実際は構造を工夫することにより、耐震基準を満たすよう耐震性を高めています。
同じ鉄筋コンクリート住宅でも建物の形状で耐震性は変わる?

構造部分を同じと仮定した場合、コの字やL字のような複雑な形状より、正方形や長方形の方が耐震性は強いです(※1)。
正方形や長方形の建物は上から下と、右から左まで、全方向に対して一様に壁が配置された構造になります。そのため、揺れによる力が均一に分散され、倒壊しにくくなるのです。
ただし、実際に世の中にある建物に関していうと、「コの字やL字だから耐震性が弱い」とはなりません。どの建物も、耐震基準を満たして設計されているためです。自由曲線を活かしたデザインでも、入念に構造計算をしているため、耐震性の高い住宅が建てられます。
※1 参考:香川県土木部建築指導課「耐震設計とは~耐震設計の基礎知識~」
鉄筋コンクリート構造の耐震性の高さが住宅にもたらす恩恵

耐震性が高い鉄筋コンクリート構造の住宅を建てることにより、以下のような恩恵があります。
強度を活かして自由に設計できる
鉄筋コンクリート造は強度の高さを活かし、以下のような間取りやデザインを選択できます。
- 50畳のLDKなどの大空間
- 曲線を取り入れたデザイン
木造住宅で実現できる大空間のLDKは30畳くらいまでが一般的です。30畳の広さが確保できても、たとえばリビングとダイニングの間に壁が必要なケースでは、開放的な空間でなくなることもあります。
また、木造や鉄骨造など基礎の上に柱を建てて住宅の形にしていく構造では、強度を保ちながら曲線を取り入れることは難しいでしょう。
曲線をデザインに取り入れられるのは、強度が高い鉄筋コンクリート造がもたらす恩恵といえます。
地震による倒壊の心配が少ない
鉄筋コンクリート造は耐震性が高いため、大地震が発生した場合でも住宅が倒壊する心配が少ないことも恩恵の一つです。
地震は、地中のプレートの境界がある付近で発生しやすいといわれています。日本は周囲にプレートの境界が4つある、地震大国です(※1)。
首都圏でも大地震発生が懸念されており、地震に強い住宅にすることは安全性を確保するために重要です。耐震性の高い鉄筋コンクリート造を採用することで、地震に備えられることも恩恵といえるでしょう。
※1 参考:東京都耐震ポータルサイト「1.大地震はいつ来る?」
耐用年数が長く住宅の資産価値が落ちにくい
鉄筋コンクリート造の住宅は他の構造と比較して耐用年数が長いことも、耐震性の高さで得られる恩恵です。
国税庁による構造別の住宅の法定耐用年数は、以下のとおりです。
| 住宅の構造 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 鉄筋コンクリート造鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |
| 金属造 | ・骨格材の肉厚が4mmを超える場合:34年 ・骨格材の肉厚が3mmを超えて4mm以下の場合:27年 ・骨格材の肉厚が3mm以下の場合:19年 |
| 木造 | 22年 |
参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
木造の22年と比較すると、鉄筋コンクリート造は倍以上の耐用年数があります。
耐用年数とは、減価償却など税務のために定められた年数を意味します。住宅の寿命ではありませんが、鉄筋コンクリート造が木造と比べてどれだけ長く資産価値を維持できるか、一つの指標となるでしょう。
さらに、コンクリートや鉄筋の劣化が進んでいても、状態に応じた適切な補修を施すことで、改修後の物理的な耐用年数を30年以上(※)延ばせるとされています。適切な管理によって住宅の強度が高い状態を保てるため、鉄筋コンクリート造には資産価値が下がりにくい恩恵があります。
※参考:文部科学省「第1章 長寿命化改修の基本的事項」
鉄筋コンクリート住宅の耐震性以外の特徴

鉄筋コンクリート住宅は、高い耐震性以外に以下のような特徴があります。
耐火性が高く火災に強い
鉄筋コンクリートは、耐火性にも優れています。コンクリートは不燃素材に該当するため、火災が発生した場合にコンクリート自体が燃えることはありません。
内部の鉄筋は温度上昇によって強度が低下する可能性はありますが、熱に強いコンクリートで覆っているため火災の影響は少ないといえます。
他の構造の住宅と比較して耐火性が高いため、火災保険料が安い点も鉄筋コンクリート住宅の特徴の一つです。
高気密によって断熱性能が高まり、快適な住空間を実現できる
鉄筋コンクリート住宅は気密性を高めることで、断熱性能を高くできることも特徴です。
コンクリートそのものは熱が伝わりやすい性質があるものの、気密性が高いため内断熱や外断熱などの対策によって断熱性を高められます。断熱性が高いと外気温に左右されずに建物内で過ごせるため、自宅が快適な住空間になります。
また、断熱性の高い住宅は空調の効率がよく、省エネにつながる点も鉄筋コンクリートの特徴といえるでしょう。
遮音性が高く騒音トラブルの心配がない
鉄筋コンクリート構造は、気密性の高さが遮音性の高さにつながるため、騒音によるトラブルを防止できます。
建物自体に隙間が少ないため、室内からの音漏れや、外部からの騒音の侵入を防止できます。楽器を自宅で演奏するような場合でも音漏れしにくく、騒音によるトラブルの心配がありません。また、外部からの音が入らないことで、1日中静かに過ごせるでしょう。
まとめ
鉄筋コンクリート構造の住宅は、横揺れに強い鉄筋で縦揺れに強いコンクリートを補強しているため、耐震性が高い建物です。
鉄筋コンクリート構造なら、耐震性が高い特性を活かし、自由曲線をデザインに取り入れられます。ただし、デザインの自由度が高い分、仕上がりが施工会社の技術力に左右されやすいため、依頼先をしっかり精査することが大切です。
山川設計は、鉄筋コンクリート構造に特化した設計事務所です。住宅を中心に数多くのプロジェクトを手掛けてきた実績を基に、多様なニーズにお応えできます。
鉄筋コンクリートで堅牢な住宅を建てたい方は、ぜひ山川設計にご相談ください。